「たった1台の霊柩車なのに、どうして私たちまで点呼をしなければならないのか……」
こうした声は、全国の霊柩事業者からしばしば聞かれます。
確かに、霊柩事業者は一般貨物自動車運送事業に含まれるものの、トラック輸送とは業務形態が異なるため、法律上いくつかの特例が認められています。
そのひとつが「点呼執行」に関する扱いです。
今回は、霊柩事業者にとって見落とされがちな「点呼」の実態と、法令を遵守するためのポイントについて解説していきます。
1.なぜ霊柩事業者は「5両未満」でも認められるのか

トラック運送会社の場合、営業所ごとに最低5両以上の登録が必要です。ところが、霊柩事業者は1両でも事業を行うことができます。
これは「貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項関係」で、霊柩自動車や廃棄物収集車など、特定の業務に限られる営業所については運行管理者の選任を義務付けないと明記されているためです。
全ての営業所に運行管理者を1名以上選任することを義務付ける。
ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長
が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の
運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるもの(専ら霊きゅう自動車の
運行を管理する営業所、専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を
管理する営業所、一般的に需要の少ないと認められる島しょに存する営業所等を想
定。)については、運行管理者の選任を義務付けないものとする。
つまり、霊柩事業者であれば、【運行管理者や整備管理者の選任は必須ではない】という特例が適用されます。
しかしここで勘違いしてはいけません。
「運行管理者が不要」=「点呼が不要」ではないのです。
2.霊柩事業者の点呼執行はどのようにすればいい?

霊柩事業者は運行管理者の選任義務こそありませんが、点呼自体の実施義務は残ります。
通常のトラック運送会社では、資格を持った運行管理者や補助者が点呼を行います。では、霊柩事業者はどうすべきでしょうか。
答えはシンプルです。
社内で「管理者」を選任し、その人物が点呼を執行することです。
管理者は、点呼記録簿を用いて「乗務前点呼」「乗務後点呼」を実施し、記録を残さなければなりません。その記録は最低1年間保存する必要があります。
特にアルコール検知器の活用や健康状態の確認は、点呼の根幹となる部分。霊柩事業者であっても、この流れを省略することは許されません。
3.少人数だからこそ直面する問題
霊柩事業者の多くは少人数で運営しています。依頼は突然舞い込むことが多く、早朝や深夜に出動するケースも珍しくありません。
このとき問題になるのが「セルフ点呼」です。
夜間に1人だけが待機していると、どうしても自分で点呼をしてしまいがちですが、法律上セルフ点呼は認められていません。
そのため、巡回指導や行政監査が入ると「点呼違反」で指摘されるケースが目立ちます。
さらに、2023年12月以降は、自家用自動車5両以上を保有する会社にアルコール検知器の使用が義務化され、世論も厳格化。
これまで「霊柩だから特例で許される」という空気は薄れつつあります。
4.霊柩事業者が守るべき“これからの当たり前”
緑ナンバーを掲げ、大切なご遺体を運ぶ霊柩事業者だからこそ、法令遵守は信頼の土台となります。
-
社内で管理者を明確に選任する
-
点呼記録簿を作成し、アルコール検知器を用いた記録を残す
-
形骸化させず、実効性ある点呼を習慣化する
これらはもはや選択肢ではなく、時代の要請です。
「トラック会社とは違うから」と考えるのではなく、「同じ公共交通を担う事業者だからこそ」という意識を持ち、法令を守ることが、霊柩事業者の信頼と持続的な運営につながっていきます。
まとめ
一般貨物自動車運送事業に霊柩事業者は含まれますが「トラック運送会社と同じ扱いでは困る」と法令遵守を疎かにしている会社があります。
ですが、その考えは時代遅れ。
現在は、行政監査は、霊柩事業者であろうと積極的に行っています。
運行管理者を選任する必要はありませんが、管理者を社内で選任し、しっかりとアルコール検知器を使用するなど、点呼記録簿を作成するようにしましょう。







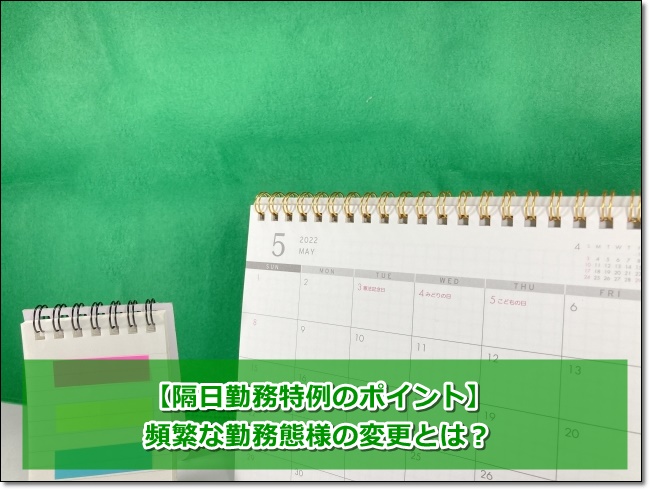
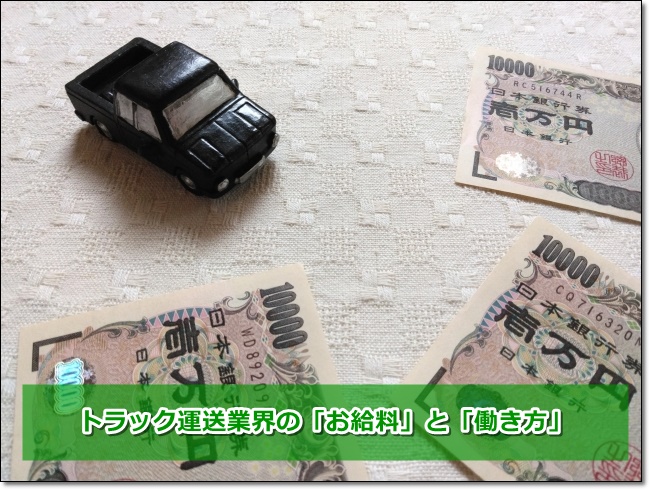
コメントを残す