運転業務に関わる方々や、事業者の皆さんにとって「改善基準告示」という言葉を耳にすることは少なくないでしょう。
この告示は、安全で健康的な職場環境を確保し、運転者が安心して働ける環境を提供するために非常に重要な役割を果たしています。
しかし、その内容や適用範囲について具体的に理解している方は、意外と少ないかもしれません。
今回は、「改善基準告示」がどのような人に適用されるのか?
またその具体的な内容について解説します。
特に、自動車運転の業務に従事する方やその関係者にとって重要なポイントを、わかりやすく説明していきます。
改善基準告示に該当する人とは?

改善基準告示に該当するかどうかについては、次に紹介する「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に記載されています。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(抄)」
第1条 この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
四輪以上の運転の業務を主として従事するものが対象になるのですね。
では、具体的にどのような人が対象になるのか、4つのポイントを紹介します。
1.給料取得者

「改善基準告示」は、労働基準法第9条に基づき、「労働者」に対して適用されます。
ここでいう「労働者」とは、同居する親族だけを雇用する事業や家事使用人を除くすべての人々を指します。さらに、この告示は「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する人」に適用されます。
では、「自動車の運転の業務に主として従事する」とは具体的にどのような意味でしょうか?
これは、実際に物品や人を運搬するために車両を運転している時間が、労働時間の半分以上であり、かつ、その業務が年間総労働時間の半分を超えると見込まれる場合に該当します。
このため、たとえば、クレーン車のオペレーターが移動のために路上を走行しても、これは「自動車の運転の業務に主として従事する」とは見なされません。
2.一般貨物自動車運送事業の役員も対象
以前は、基準の第1条に記載されているとおり、改善基準告示の対象者は「労働基準法第9条に規定する労働者(=給料をもらって働いている人)」と記載されていますので、社長が「(自身は)改善基準に関係ないので、長距離輸送は私が行っている。」という人もいました。
ところが、平成30年4月20日に輸送安全規則の解釈・運用が改正されたことにより、社長などの役員も改善基準告示の対象となることになりました。
[貨物自動車運送事業の解釈及び運用について](抜粋)
(第3条第4項関係)
(1)事業者が運転者(個人事業主、同居の親族及び法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下「事業主等」という。)が運転する場合には、当該者も含む。)の勤務時間及び乗務時間……以下略…
なお、事業主等が運転者として選任される場合の拘束時間は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)で定める労使協定の締結をお子合っている場合にあっては、当該労使協定により延長することができる範囲を超えないものとすることとする。
支局に確認しても、やはり、「社長が運転業務をする場合の拘束時間は、改善基準告示の対象になる」との回答でした。
そのため、社長が運転したとしても改善基準告示違反していれば、巡回指導や行政監査で他の労働者と同様に指導を受けますので、注意してください。
3.4輪以上の車両であれば、自家用自動車を運転する労働者にも適用

改善基準告示は、運送業としての運転者に限らず、一般企業の自家用自動車を運転する労働者にも適用されます。
具体的には、製造業における配達部門で自動車を使用する運転者などがこれに該当します。
このような場合、貨物自動車運送事業者に適用される基準(改善基準告示第4条)を準用し、同様の基準が求められます。これにより、すべての運転者が労働時間や勤務条件を守り、過度な負担を防ぐことが求められるのです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
すべての人が改善基準告示に該当するわけではなかったんですね。
なかには営業ナンバーだけでなく白ナンバーも該当することに驚いた方もいたと思います。白ナンバーだから大丈夫と思ってた方は気をつけておいたほうがいいですよ。
[hana-code-insert name=’ad3′ /]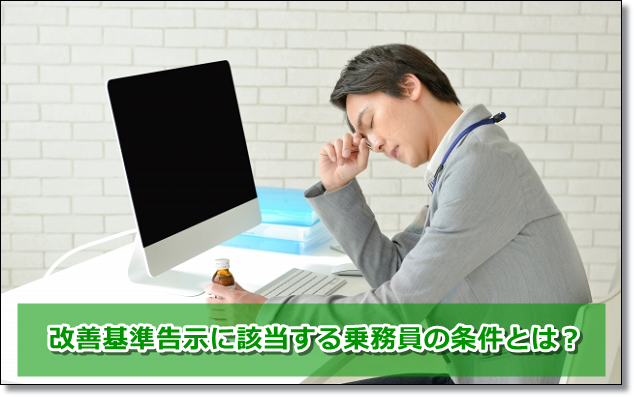


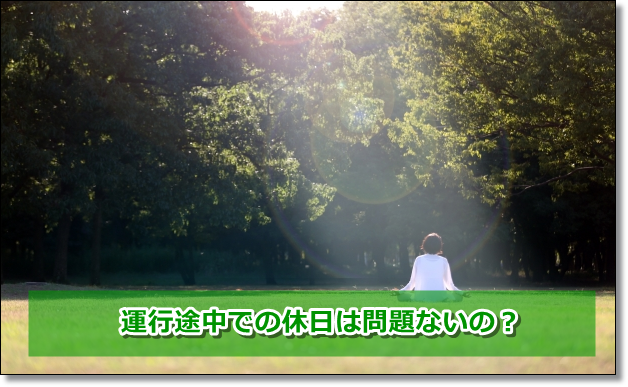

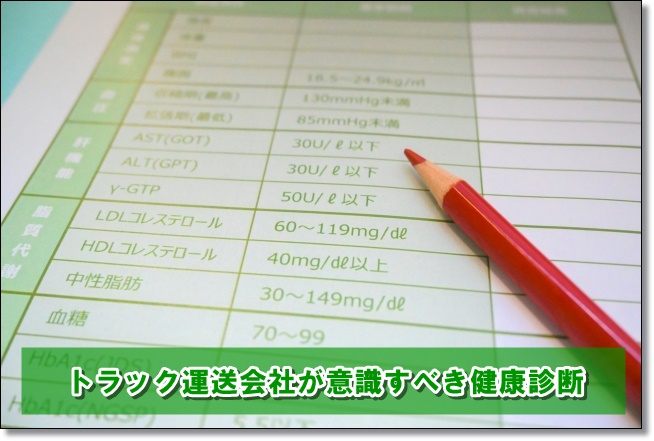

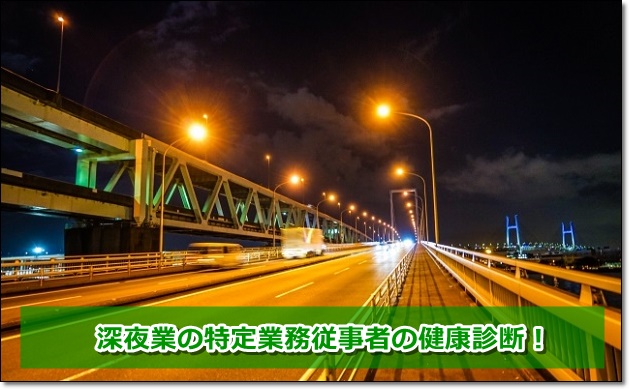
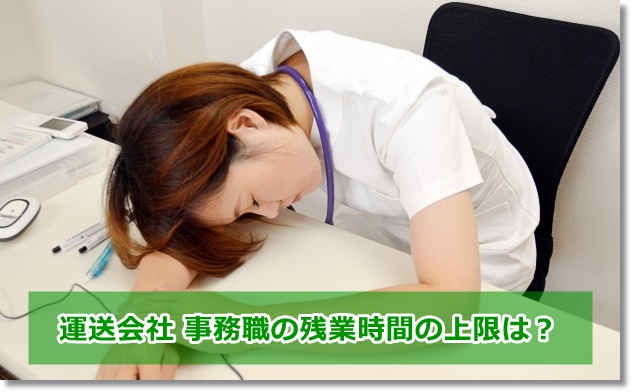
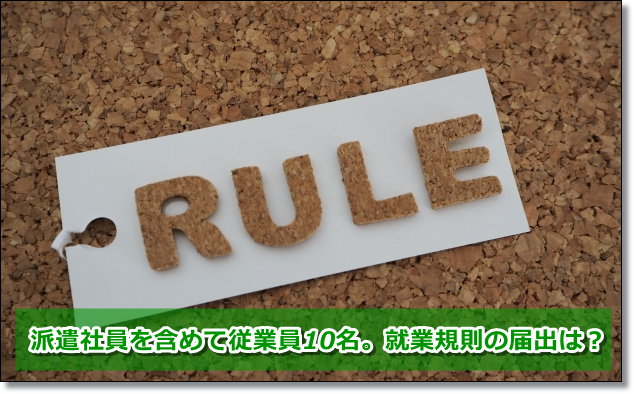




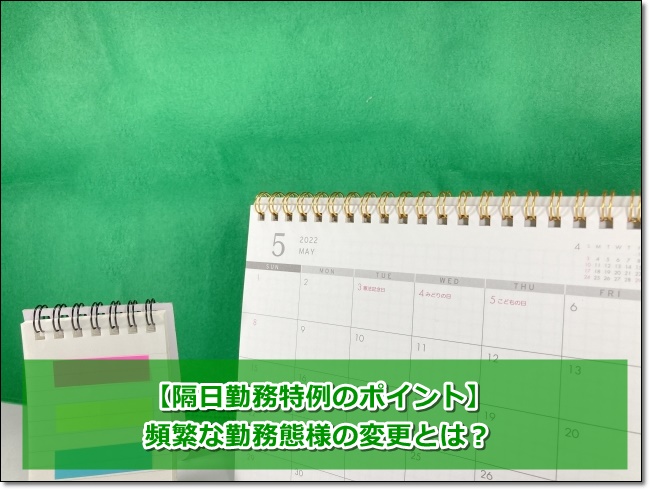
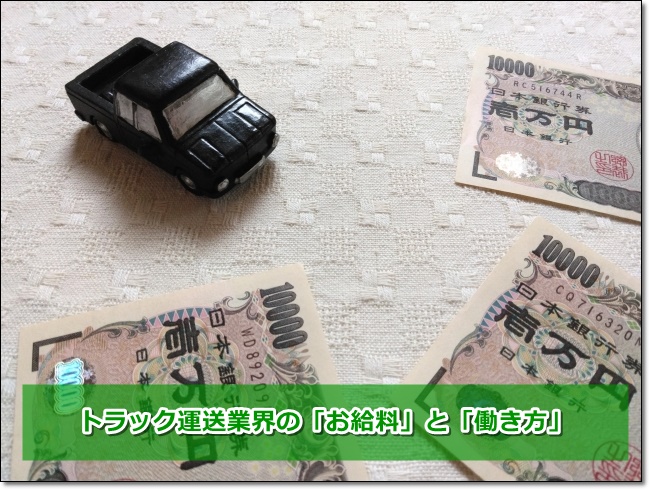
目的だけを読めば確かに白ナンバーも該当します。
しかし、第2条以降の条文には旅客や貨物と明記されています。
青ナンバーを対象としていると思いますが?
第4条に貨物自動車運送事業のことが詳細に記載されています。
最初は事業法に適用される運転者について記載されていますが、
第4条6に
前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業をいう。次条において同じ。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。
と書かれていますので、貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者も適用されるということになります。
改善基準に違反した場合、運行管理者本人にお咎めはないのか?
現実には休息期間の8時間を守ろうとすれば、運行管理者は、その次の勤務も変更が必要だし…。しかし、現実には中々出来ないのが現状だと思う。
普段の無事故ならば大丈夫だろうが、大きな事故を運転士がやってしまった場合、行政から運行管理者本人にお咎めはないのか?会社が処分されるのは当然としても、それは現実にはどうなのか?